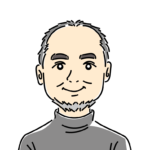
今回は、ビジネスTipsとして会議のファシリテーションについてです。会議を円滑に進めるために、どのように振る舞うべきか、ファシリテーションのコツについてまとめてみました。
この記事のポイント
- 会議の質を高めるには、ファシリテーターの工夫が鍵を握ります。
- 明確なゴール設定や参加者全員の巻き込み方など、実践的な6つのコツを解説します。
- 各ポイントに事例や具体的フレーズを盛り込み、すぐに取り入れられる内容になっています。
会議の価値を引き出すために必要なこと

現代のビジネスシーンでは「会議疲れ」や「ムダな会議」が問題視されがちです。「何の結論も出なかった」「一部の人だけが発言して終わった」といった状況に、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
そんな会議を変える鍵が「ファシリテーション」です。進行役であるファシリテーターが少し意識を変えるだけで、会議の雰囲気や成果は大きく変わります。ここからは、建設的な会議を生み出すためのファシリテーションのコツを6つの視点からご紹介します。
1. ゴールを明確にする:会議の“目的地”を共有する
会議の冒頭で「この会議で何を決めたいのか」「どんな成果を得たいのか」を明言することで、参加者の意識が一気に引き締まります。ゴールがあいまいだと、発言が拡散し、収拾がつかなくなる原因になります。
- 「今日は来期の新サービスの方向性を3案に絞ることがゴールです」
- 各部署からの課題を共有し、次回の打ち手に優先順位をつけます」
- 会議招集の段階でアジェンダを共有しておくと、参加者が事前に考える時間を確保できます。
- ゴールは紙やスライドに書いて会議中も常に見えるようにしておくと効果的です。
2. 議論の構造を常に描く:話の流れを「見える化」
議論が盛り上がってくると、どのテーマがどのように繋がっていたのか分かりづらくなります。そこで、ホワイトボードやオンラインツール(Miro、Jamboardなど)を活用して、議論の地図を描くことが大切です。
- 論点をリストアップし、「今どの論点を議論しているか」を明示する。
- MECE(漏れなくダブりなく)やロジックツリーでアイデアを整理する。
- 意見の分類(賛成・反対・保留)を色分けして視覚的に整理する。
事例
ある新製品開発会議では、製品コンセプトに対する意見を「ユーザー視点」「コスト面」「技術的実現性」の3軸に分類したところ、議論が具体的かつ多角的になりました。
3. 均等に話を聞く:全員が参加する場づくり
一部のメンバーだけが議論をリードするような状況は避けたいところです。特に静かなメンバーの中にも、実は鋭い視点やアイデアを持っていることがあります。ファシリテーターは、そうした声を引き出す工夫をしましょう。
- 「この点について、○○さんはどう感じますか?」と名指しで声をかける。
- 4人程度のグループに分かれてディスカッションし、その内容を発表させる。
- ポストイットなどで意見を事前に書かせてから共有する。
発言のしやすさは心理的安全性にも関わるため、否定的な反応を避けるなど、安心できる雰囲気づくりも重要です。
5. 定期的に振り返る:議論の方向性をそろえる
議論が発散していると感じたら、途中で立ち止まって内容を整理・要約しましょう。これにより、参加者全員の理解と認識をそろえ、次に進むべき方向が明確になります。
- 「ここまでをまとめると、A案にはコスト面の懸念があるということですね」
- 「この観点は重要そうです。他にも同じ意見の方はいますか?」
- 5〜10分ごとに「まとめポイント」を設ける習慣をつけると、自然と会議全体が整理されます。
6. 時間をマネジメントする:会議の濃度を高める技術
時間通りに終わらない会議は、参加者の集中力や信頼感を損なう原因になります。事前にアジェンダごとの時間配分を決めておき、進行中も意識して調整するようにしましょう。
- 「この議題には15分使いましょう」と宣言して始める。
- 議論が長引いた場合は「次回に持ち越す or 別途タスク化する」判断をする。
- 専任のタイムキーパーを設定する。
- 時間配分は柔軟に運用しつつも、全体の終了時間は厳守することが大切です。
まとめ
ファシリテーションの目的は、参加者一人ひとりの知恵や意見を最大限に引き出し、合意形成をスムーズに進めることです。
1.ゴールを明確にする
2.議論の構造を見える化する
3.均等に意見を引き出す
4.問いを投げかける
5.定期的に振り返る
6.時間をマネジメントする
これらを実践することで、会議が単なる話し合いではなく、価値ある成果を生む場へと変化します。
次回の会議では、ぜひこれらのテクニックを意識してみてください。ファシリテーターとしての一歩が、チーム全体の成長につながります。



